- English
- 日本語
【中編】価値観の異なる人が協働する方法を学びたい
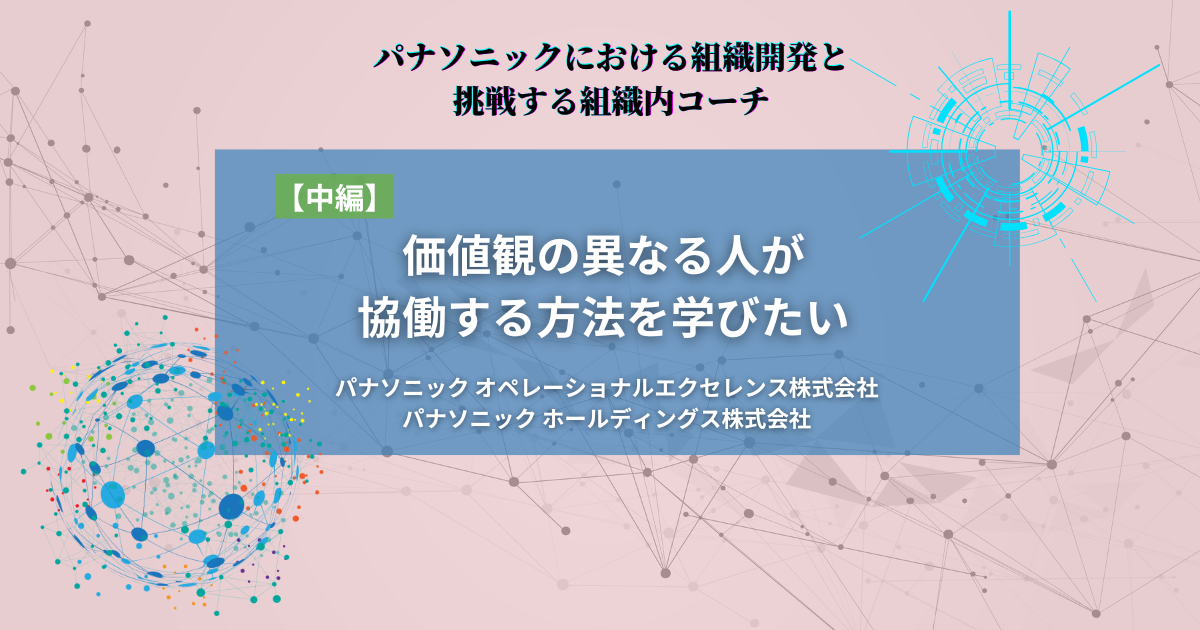
パナソニックにおける組織開発と挑戦する組織内コーチ / パナソニック オペレーショナルエクセレンス株式会社 パナソニック ホールディングス株式会社
【前編】組織開発を本気で進めようという経営の意志
【中編】価値観の異なる人が協働する方法を学びたい(今この記事を読んでいます)
【後編】ORSCの取り組みが「バタフライ効果」に
組織内コーチが増えている今、どうORSCを活用し、組織で展開しているかについて、精力的に活動を進めているパナソニック オペレーショナルエクセレンス株式会社の戒能直美さんと小濵玲子さん、パナソニック ホールディングス株式会社の宮下航さんの3人に引き続きお話を伺います。
ぐるっと回って一番大事なのはDTA
――ORSCを学び始めたきっかけや学んだことについて聞かせていただけますか?
戒能さん:私は2022年に受けた「組織内チームコーチ養成コース」のインタビューの時にお話ししましたが、組織開発推進室の元室長の前川さんが組織開発の支援へ行った時にORSCの知恵を使っているのを見て、「私もやりたい」と興味を持ったのがきっかけです。
事業場の支援をしていく中で、組織開発の肝はメンバー同士や上司・部下の関係性で、そこを何とかしたいと思った時にORSCが使えると思いました。
【前編】なぜ「組織内チームコーチ養成コース」に参加したのか?

小濵さん:私は元々デバイスの海外営業なのですが、新入社員研修でチューター役をさせてもらったときに初めてコーチングという言葉と出会いました。当時、リーダーシップについてすごく考えていて、「それぞれのリーダーシップなるものが発露している時が人が輝いている時」だと思うに至りました。そこから「リーダーシップを発揮するとは、何をすることなのだろう?」という問いが生まれ、リーダーシップを伸ばしていくのにコーチングが役に立つのではないかと思いました。
初めに勉強し始めたのはパーソナルコーチングだったのですが、組織で「こんなことをやろう」となった時に、1人1人にアプローチをするパーソナルコーチングだけでは足りない気がしたんです。そんなモヤモヤを抱えていた時にチームに対するコーチングがあると聞き、2013年秋にORSCの基礎コースへ行ってみることにしました。

そこで感じたのは、ORSCは人とチームのリーダーシップの道、タオだということです。1人1人の変化に呼応して、場全体が変わっていきます。それが誰かの一言によって一瞬で変化する時もあれば、じわじわ変わっていく時もあります。ORSCを通じて確実に何かが変わる、それがチームで起こるんですね。
ORSCには色々なスキルやツールがありますが、チームにとって一番大事なのは、ぐるっと回ってDTA(Designed Team Alliance)だと思います。その根底にあるのは、「誰もが正しい。ただし一部だけ」というORSCの考え方、哲学です。
思考回路が違うことによって話が通じない
――宮下さんもORSCを学び始めたきっかけや学んだことを聞かせていただけますか?
宮下さん:先程、「共創ラボ」の運営をしているという話をしましたが、新規テーマの創出を伴走する中で、事業創出のプロセスだけではチームがうまく回らないという課題を感じています。
イノベーションを考える上で、チームにはBTC人材――ビジネスの人、テクノロジーの人、クリエイティブデザインの人――を混ぜることが大事で、違いをどのように活かすのかという観点からも大切だと言われています。
そうした人々のリーダーシップやチームビルディングを見ながら伴走していくのですが、例えば、デザイナーとエンジニアの思考回路はかなり違うんですね。デザイナーはAとBという全く関係のない事象があると、積極的にそれを掛け合わせて意味付けをします。ポンッと出てきたとか、降ってきたという感覚的なものを表現することも多いです。
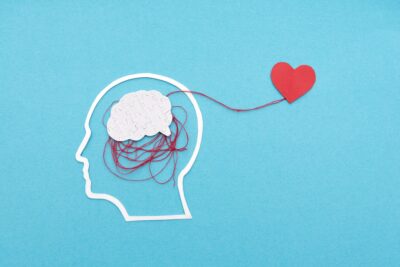
一方、エンジニアは再現性が重要なので、構造や原因を特定して考える傾向があります。「それはなぜか?」「それはどういう構造か?」とロジックで詰めて、分析をするんです。そうするとデザイナーとエンジニアが同じものを見たときに、お互いの見ている世界が違うので全然分かり合えないということが頻繁に起きます。
お互いにその根底にあるものがわからないと本当に話が通じなくて、チームがうまくいかなくなってしまうことがあります。そうした経験をすることで、価値観が違う人が協働するための正しい方法を知りたいと思うようになりました。
組織開発推進室の前川さんと戒能さんに相談したところ、ORSCという手法があると教えてもらい、2022年から基礎・応用・実践コースへ行き、2024年にORSCC(Organization and Relationship Systems Certified Coach)の資格を取得しました。
人と揉めない僕が得た新しいレンズ
宮下さん:ORSCでは様々な学びを得ました。それまで僕自身、コーチングについてそんなに詳しくなかったんですね。その瞬間、瞬間に起きているものをどうやって捉えていくのかという視点もあまり強くありませんでした。
特に大きな学びだったのは、「気づいているけれど避けてきた」という自分自身のエッジ(変化の妨げになる心の障壁)が見えたことでした。例えば、コミュニティの中で、僕は人と揉めないように行動するんですね。怒りや悲しみの感情は苦手なので、そういう対立を意図的に避けてきてところがあって。ですが、怒りや悲しみの裏には強い願いがある。そこから逃げずにとどまって、そこにある何かをちゃんと燃やしきって、その先に行くことで現状が良くなるという視点をもらいました。
それによって僕にはなかった新しいレンズをもらったんです。ここがORSCを学んで一番インパクトがあったことでした。そのレンズがあると対立の場でも冷静に相手のことが見られるし、その奥にある痛みや願いなど目に見えないものへの想像力が上がっていくので、相手への解像度がすごく上がったという感覚があります。よりマイノリティ側の意見に耳をすませるように関わり方が変わりました。
地域や社内外でのファシリテーションの場でも、EQ(感情的知性)、SI(社会的知性)、RSI(関係性システムの知性)という、個人、他者、関係性システムに何が起きているかを言葉にし、そのシステムに効果的に働きかけながら進めることができるようになり、ファシリテーションの力がぐんと上がりました。

自分自身のエッジが見えた宮下さん
【後編】では、戒能さんと宮下さんが行っている「ワールドワークプロジェクト」*について伺います。
* ORSCの知恵を使い、目の前に起きているさまざまな問題・課題に働きかけ、より良い関係性(Right Relationship)を共に作ろうとする取り組み
