システムコーチングとは?~組織内チームコーチの視点から見た関係性の力~
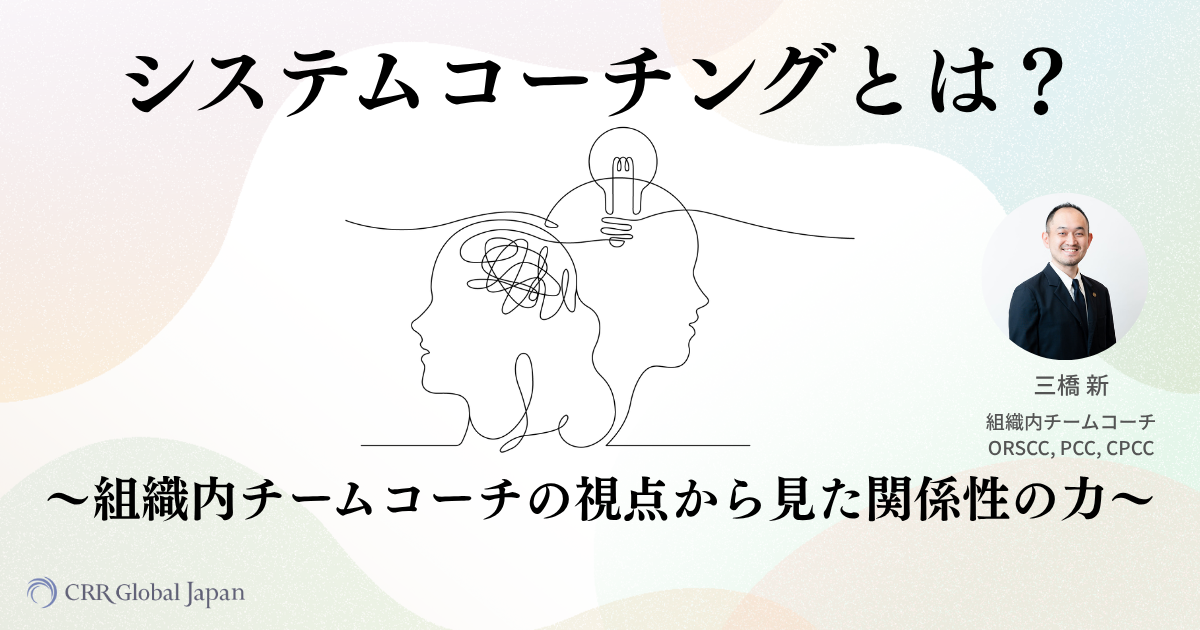
目次
システムコーチングとは?組織の“関係性”にアプローチするコーチング手法
私はこれまで10年以上にわたり、企業内でコーチングを提供してきました。 当初は主に個人に対する1対1のコーチングが中心でしたが、 やがてチームや組織全体の課題に対する支援の必要性を感じるようになりました。
その結果、近年では、関係性に焦点を当てた「システムコーチング」を中心に提供しています。 社内ではコーチングの認知も進み、私以外の社内コーチも育ち、 多くの社員が気軽にコーチングを受けられる環境が整いつつあります。
このような背景の中、私が問い続けてきたのは、 「なぜ今、企業において関係性に焦点を当てたコーチングが必要なのか」ということです。

本記事では、企業内での実践経験をもとに、 関係性に注目したシステムコーチングとは何か、 なぜ企業にとって有効なのかを考察し、変化の実例も交えて解説します。
なぜ今、企業でシステムコーチングが必要なのか?
組織において問題や課題が発生したとき、多くの場合、その原因は個人に帰属されがちです。 「誰の責任か」「どのスキルが不足しているのか」「どのような教育が必要か」 といった議論が主流になるのは、 人事評価制度やマネジメント手法が個人の成果や行動に焦点を当てて設計されているためです。
しかし、現場で実際に起きている課題は、必ずしも個人の問題とは限りません。 たとえば:
- チーム内での意思疎通がうまくいかない
- プロジェクトが停滞してしまう
- 部門間で連携が取れない
このような問題は、多くの場合「関係性」に起因しています。
関係性とは、人と人との間に存在する相互作用のパターンです。 これには次のような要素が含まれます:
- 言葉にされない期待や恐れ
- 役割への無意識な同調
- 組織内の歴史的背景や文化的要素
システムコーチングでは、こうした関係性を「システム」として捉え、 個人ではなく関係性そのものを支援の対象とします。 この視点の転換により、これまで見過ごされてきた組織の構造的な課題が浮かび上がります。

システムコーチングの効果:関係性への介入がもたらす組織変化
関係性に意識的に介入することで、個人の能力を変えることなく、 組織全体のパフォーマンスを高めることが可能になります。
事例1:部門間の対立の改善
あるチームでは、部門間の対立が顕在化していました。 システムコーチングの導入により「共通の目的」についての対話を行ったところ、 対立の背景にあった誤解や不信感が解消され、業務連携がスムーズになりました。
事例2:上司と部下の信頼再構築
別の組織では、上司と部下の間で期待のすれ違いが生じていました。 お互いの立場や思いを言語化するプロセスを通じて、 信頼関係が再構築されました。
このように、関係性を改善することは、 個々の行動変容だけでなく、組織文化全体の変化をもたらします。 関係性への介入は、単なる問題解決ではなく、 未来に向けたチームの共同創造の基盤を整える取り組みです。
本音が語られる職場環境をつくるシステムコーチングの力
企業では、「本音で話すことが難しい」という声をよく耳にします。 本音とは、建前や遠慮を取り払った、率直で誠実な感情や意見のことです。
しかし現実には:
- 会議の時間が限られている
- 社歴や役職の上下関係がある
こうした状況の中で、本音が語られる機会は少なくなりがちです。
さらに、本音を語っても、相手に受け止めるスキルがなければ、 対話は成立しません。その結果:
- 「言っても無駄だ」
- 「分かってもらえない」
と感じ、沈黙や回避行動につながってしまいます。
システムコーチングでは、本音が語られる場を意図的に設計します。 コーチは、感情や感覚を安全に表現できるよう支援し、 対話の質を高める場を提供します。
このような場では、個人が内面を語り、他者との違いを認め合うことが可能になります。
本音には、葛藤や悲しみ、不安といったネガティブな感情も含まれます。 それらを共有することで共感が生まれ、 メンバー間の関係性が深まり、組織課題にも協力して向き合おうとする意識が育まれます。

DTA(Designed Team Alliance)とは?協働関係を築くための合意プロセス
私が企業内でシステムコーチングを実施する際には、必ずDTA(Designed Team Alliance)という手法を導入します。DTAは、チームが意図的に協働関係を築くための合意プロセスであり、関係性を自律的にマネジメントするための枠組みです。
多くの会議では、進行役となる一部の人が意図を持ち、その他のメンバーは受け身で参加している状況が見受けられます。DTAでは、全メンバーが会議の目的や進め方について合意を形成し、その合意に基づいて会議を進行します。これにより、参加者全員が主体的に責任を持って関わるようになります。
DTAを導入することで、日常のコミュニケーションにおいても「どのような関係性を築きたいか」をメンバー同士で共有する習慣が生まれます。これはチーム全体の自己認識を高め、継続的な関係性の改善へとつながります。
組織内コーチの役割とは?関係性を可視化し支援する存在
組織内コーチの役割は、組織で何が起きているのかを明らかにすることです。 これは、単なる現状把握ではなく、 個人の感情や感覚、行動パターンなどを含めた多層的な現実を可視化することを意味します。
組織が自らの状態を理解し、自覚することで、 課題解決に向けた意思決定が可能になります。 このプロセスを支援するのが、組織内コーチの役割です。
コーチは組織の一員として、内側から関係性を観察し、 変化の兆しを見逃さずにフィードバックを提供します。 このような継続的な関わりが、組織全体の学習と進化を促進します。

おわりに:関係性に意識を向けるという選択肢
パンデミックを経て、働き方は急速に多様化しました。 リモートワークと出社の混在、デジタル化による情報の非対称性、 世代間の価値観の違いなど、組織運営の難易度は一段と高まっています。
「戦略は明確だが、現場での実行がうまくいかない」と感じる場面は増えています。 その背景には、関係性が影響しているケースが少なくありません。
私は、関係性がすべての答えだとは考えていません。 しかし、他の方法ではうまくいかなかったときに、 関係性に意識的に働きかけることで、 状況が大きく変わることを何度も目の当たりにしてきました。
もしこの記事を読んで、「システムコーチングとは何か」に関心を持っていただけたなら、 ぜひ説明会にお越しください。 現場での体験を通して、関係性の持つ力を感じていただければと思います。
